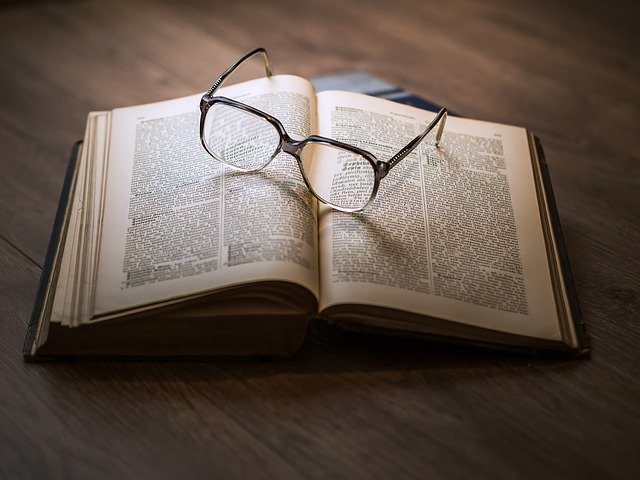![]()
![]()
![]() 会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは
会員募集 ご寄付 お問い合わせ AGRI FACTとは
本サイトはAGRI FACTに賛同する個人・団体から寄付・委託を受け、農業技術通信社が制作・編集・運営しています
【動画】(化学物質の)毒性の閾値はどうやって決める? 【東京大学名誉教授の唐木英明先生に聞きました!】
渕上 先生!(毒性が)人体に影響があるかどうかという閾値(いきち)についてはわかったんですけれども、その閾値がどのくらいかというのは、それはどうやって決めているものなんでしょうか?
唐木 これは、実験動物を使って実験をします。その農薬を与えて、どんな毒性が出るかを調べる。量をどんどん減らしていくと、なんの毒性もない量というのがわかります。これを「無毒性量」といわれます。
渕上 無毒性量?
唐木 はい。だから、毒性が出ない量よりも下だったら、何の影響もないはずですけども、これは実験動物の話です。人間はそれとは、違うかもしれない。だから、動物と人間の違いは「10分の1」。10倍あるとして。人間でも年寄と若い人の違いが10倍あるとして、100倍違いがあると考えて、実験動物で、なんの毒性もない量の100分の1を人間での何も影響がない量にして決める。これが、人間で言う「ADI=1日摂取許容量」という量なんです。
渕上 ADI?
唐木 ADI=1日摂取許容量。この1日摂取許容量以下であれば、全く安全というふうに考えられる。と言うのは、この 1日摂取許容量=ADIが、「人間の閾値」と考えているということなんですね。
渕上 そのADIが、念のため100分の1の量に設定されている?
唐木 実験動物で、何も毒性がでない、そのまた100分の1に(設定されている)。
結論 実験動物で何の毒性もない量の100分の1を、人間に何も影響がない量にして決める
参考